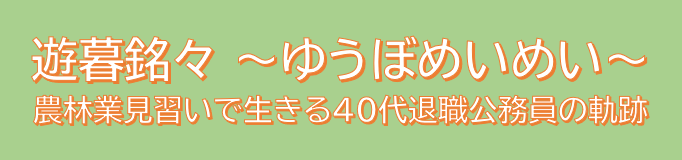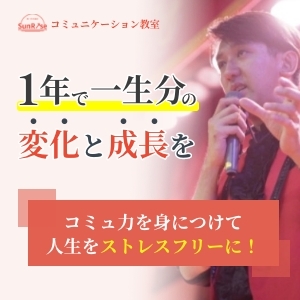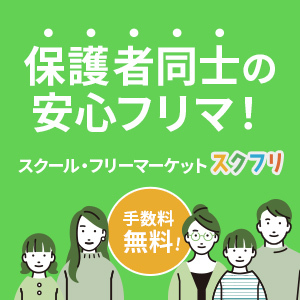小屋作りワークショップ(その3 一気に屋根を仕上げる!)
基礎と床板、そして外壁まで突貫で作ったあの日から2週間。
次の講座を予定していた日が・・・大雨☔。
空模様がヤバいとは思っていたけど、主催者さんの判断で翌日に順延となって、無事3日目の講座が始まった。
.jpg)
現地に来てみると、ブルーシートを張ってはいたものの、雨でかなり濡れていた。
みんなでシートを剥がすところから、今日の講座が始まる。
中2週間の間に、主催者さんと講師の大工さん、そして経験者のボランティアさんの手で、残る2面の外壁そしてドアと窓ができていた。
更に、屋根の下地となる角材(垂木(たるき))を差し込むための溝も、外壁を切って加工してくれていた。

3面が固定できれば、控え柱は外します。

外壁を立ち上げ、四隅をみんなで釘打ちした後は、防水シートを張る作業。
ぐるっと一周したら、次は足場を組んで上の段を一周させる。
更に三角屋根の部分(妻壁)にもシートを張るので、シートを切る必要も出てくる。
これも下地を整える大事な作業。

.jpg)
上のシートを張るときは、下のシートが隠れるように張って、雨水が壁面に流れ出ないようにします。
屋根の下地を作る。
屋根のてっぺんに取り付ける棟木(むなぎ)を加工する。
屋根の傾斜に沿って、板材を角度をつけて面取りする。
傾斜をどうするかは、大工さんの判断。
しっくりくる感覚、というのがあるのだろう。

加工した棟木を差し込む。
棟上げは建物を作るときの要。
一般の住宅でも、「上棟式」といわれる工事の労いと完成祈願の儀式をするくらいだから、厳格で神聖なプロセスなのだろうと思う。
これがずれてしまうと後の屋根作業にも狂いが出てくるから、棟木だけは大工さんの手で仕上げる。
素人には手を出せないなあ・・・

棟木を取り付けたら、屋根の下地となる垂木をみんなで取り付けていく。
垂木を付けるスパンは455mmとしているけど、実際に溝に差し込んでいくとキツかったり緩かったりする。
金づちで叩いたり、薄く切ったりして微修正しながらも、大きな問題もなく垂木の取り付けが終わる。

並行して、講師の大工さんがドアや窓枠をはめ込んでいく。
調整が必要な作業はプロの手で。


ドアをはめ込むために、ある作業をしている。

重りのようなものを垂らしているが、これは「下げ振り」と呼ばれ、垂直になっているかを確認する道具。
DIYでは、気泡の入った蛍光色の管がついた水平器はよく使われる。

しかし下げ振りは使う頻度は少ないとはいえ、こうした小屋やデッキを造る上で垂直をとる作業は必要不可欠だといえる。
更に屋根の下地づくりは続く。
脚立や足場を使う作業だから、安全面にも注意を払う。

屋根の施工は雨風をしのぐ意味から重要なため、講師とアシスタントの大工さんが中心となっての作業です。

この作業は足場も使いながら、みんなで共同でビス打ちをしました。
この後、屋根にトタンを張る前段階として、野地板(のじいた)という下地の板をみんなで釘打ちして張り付けた。
これも人海戦術。
もちろん足場を使っての作業だけど、足場から手を伸ばしても野地板の下半分くらいしか手が伸びない。
釘打ちするにも体勢が不安定。
だから、野地板の上半分は、脚立を伸ばした梯子を使って、屋根のてっぺんに大工さんほか受講生数人が上って釘を打った。
危なっかしくも思えるけど、高いところが好きな人もいるからね( ̄ー ̄)ニヤリ

野地板張りまで仕上げて、3日目は終了。
あとは最終日、トタン張りと下見板という外壁張りが待っている。
ずっと曇り空でそれほど暑くはなかったものの、湿気は高く、夕方になると蚊やアブが大量に飛んでくるものだから、虫をよけるのにも精いっぱいの一日だった。
僕も普段外仕事をしているから、虫への耐性はできているはずだけど、いざ山の中となると、飛んでくる虫もスズメバチとかもいるから、なんとも油断できないものだ。
冷や汗。
腕や足首を所々蚊に刺されて、かゆみを我慢しながらも、今日も1時間半の帰路につく。
明日の朝も同じ道を走って会場に向かうさ。

今日わかったこと。
3日目の写真を見て、部材の呼び名を勘違いしていたので整理したく、資料をリンクいたしました。
間柱の補足ですが、外壁を仕上げるために打ち付ける下地であって、重力がかかる構造材ではありません。
そのため、間柱の長さが足りなければ端材でつなげばよく、つなぎ目に数ミリ隙間があると、むしろ雨水がつなぎ目の先まで滴りにくくなるので、隙間なく打ち付ける必要はないそうです。