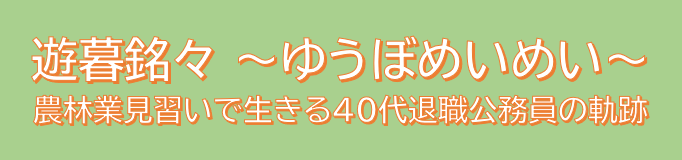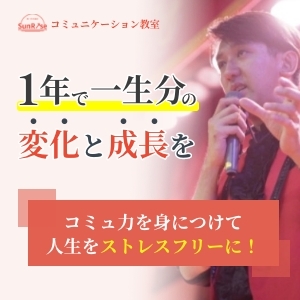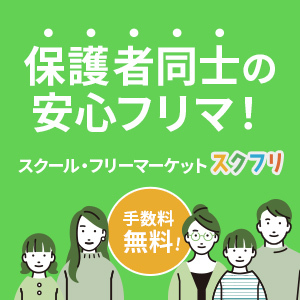梅仕事の時期、到来。失敗しない梅干しは土用干しが肝心。
僕のブログの第1回めが、去年6月の「梅仕事」だった。
梅の収穫を迎える6月。
この時期にしか出回らない、生の梅を手に入れて梅干しや梅酒などの保存食を仕込むという、ニッポンの古き良き習慣。
この習慣が、生きること暮らすことに直結しているから、梅の「仕事」と言われるのだろう。
僕も自給自足、つくる暮らしというキーワードに敏感になったのもこの頃で、自分で何かを生み出したいという想いで始めたのが梅干し&梅酒づくり、だったのを思い返してみた。
そこで教訓を得たのが、「梅干しづくりは難しい」ということだった。
梅酢が浸かるところまでは上手くいったけど、天日干しが上手くいかなく、結局カビを生やしてしまったのだ。
何とももったいないこと😢

それでも梅酒は上手くできた。
秋には琥珀色に仕上がり、満足の結果が得られた。
あのカビ悲劇から1年。
新たなコミュニティに家族共々加わり、梅仕事の先生から直接教わる機会が得られたのは何ともラッキー!なこと。
梅を使った料理を口にしながら、いよいよ講座が始まる♪


熟していない青梅は梅酒用に、熟して黄色がかった梅は梅干しやシロップ用に使います。





梅の分量の18%が標準といわれますが、減塩志向の方は塩を10%とかに減らす代わりに、アルコール等の消毒を入念にする必要があります。
せっかく梅の先生から習うのだから、失敗はしたくない。
僕も慎重に作業をして、ジップロックの封を閉めて、重石を載せて梅酢が浸ってくるのを待つ。
(重石の重さは梅の2倍以上がよいです。今回は1キロの梅に2.5キロの重石を使いました。)

塩と重石の作用によって浸透圧がかかって、梅酢と呼ばれる酸っぱい液が浸っていくわけだけど、いつまで浸しておけばいいのか?
いつになったら梅を取り出して天日で干せばいいのか?
そのタイミングを誤ると、カビが生えて失敗してしまう。
特に北海道では日光が弱いから梅干しがきれいに仕上がりにくい、という話も聞いていたから、どの時期に干せばいいのかを調べたところ、
「土用干し」
つまり、夏の土用とは「立秋までの18日間」ということで、7月20日過ぎから、ということがわかった。
この土用の時期に、しかも晴天が3日続く日を狙って天日干しをすれば上手くいく、らしい。
まあ、最近は天気が読めないから、ガチガチにこの日じゃないといけない、ということはないんだろうけど。
いずれにせよ、あと1か月以上は梅酢に漬けておいて問題ない、ということがわかったから、浸かり具合を見ながら気長に待てばいいんじゃないのかな~。
(梅仕事については多くのサイトがありますので、気に入った、納得したサイトの情報をもとに仕込んでみてくださいね。)
和歌山の梅農家さんの一品。
本物の、本場モノの梅干しは偽りのない酸っぱさ!が売りですね。